


石持観音堂
令和辛丑年九月二十一日
寒河江八幡の鎮座する長岡山の北東、石持町の街道から小径を一軒だけ入った所に「東昌庵跡」の石標を立てた御堂がある。
宝形造の本体に入母屋をあらわに加えた様な屋根。隣の公民館の小さなバス停には、積雪のため車両が停留所まで入れない云々と、気の早い注意書き
...
金峯山東昌庵は天和二年、黄檗宗の石門元通和尚によって開かれたと云う。
石持には後に慧日山梅龍寺も建てられ、当地の黄檗禅の拠点となっていたらしい
...
#
六番と刻まれた如意輪尊の石仏に手を合わせ、硝子越しに堂内を窺う。中央の厨子が本尊千手観世音か。
両脇の像はよく見えず、左の毘沙門天はどうやら背が高すぎて、傍に寄らねば幕に隠れた御顔は拝めぬ様子
...
御詠歌が五つほど書いて張ってあった。題のみ記すと、二十九番石持寺、毘沙門天、十六番わすれずも、八十八番なむやくし、ありがたや高の山。
後の三首は四国遍路のもの、当庵は寒河江八十八所の第十六番でもある
...
#
二十九番とは寒河江三十三所の事だと思ったら、別の三十三所でも二十九番であったらしい。
他の史料では更に異なる巡礼の十四番、こちらは梅龍寺の名で連なる。六番も二つ。幾つもの霊場に選ばれて、多くの参拝を迎えたか
...
梅龍寺は焼失廃寺となり、当地を去った黄檗宗の遺香は、山岸の毘沙門堂と石持の観音堂に護持されてある。
寒河江拾ヶ所第六番の御詠歌に、里もゆき山をも越へて金峯山の ほとけの誓ひ頼まぬはなし
...
■寒河江市史編纂委員会『寒河江市史編纂叢書 第六十一集』1999年
■寒河江町並研究会『昭和30年ころの寒河江町並図』2007年
■宇井啓『さがえ風土記』2010年
■宇井啓『さがえ風土記 II』2015年
■宇井啓『さがえ風土記 IV』2019年
■寒河江町並研究会『昭和30年ころの寒河江町並図』2007年
■宇井啓『さがえ風土記』2010年
■宇井啓『さがえ風土記 II』2015年
■宇井啓『さがえ風土記 IV』2019年
2022-05-30
previous . . .
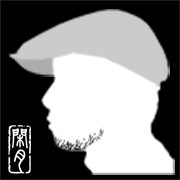
TOM
ぽんとけりゃにゃんとなくよーいよい
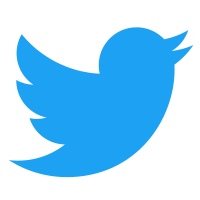 @rondino2106
@rondino2106
