



鮎貝観音 置賜第十六番
五月十日
鮎貝に入って先ず相応院へ、関寺と高岡の朱印を頂戴した。御寺の山号は朝日山。黒鴨から大井沢への参詣道を開いた道智法印を開山とする。
境内の薬師堂は置賜新四国八十八所の一つらしい
...
終えてぐるりと坂を降り登ると忽ち鮎貝観音。道路を挟んで駐車可能な余地があり、その端から更に下へ、地味に階段が付けてある。
資料に記される「肩切り地蔵」は此の階段を下った所。日清戦勝祈願の金剛山碑が目立ち過ぎている感じ
...
深山観音 ── 相応院 ── 鮎貝観音
#
御堂の内を窺うと小振りな厨子が開かれて、黒い聖観世音の姿を拝す。暗くても見える様、懐中電灯も用意してあった。
まつかわのはるばるなみをながむれば きよきながれにすずしかるらん。最上川を松川と呼ぶのは上杉領ならでは
...
御堂の隣は墓地で、今回は寄らずに済ましたが、藩政期に代々鮎貝城代を勤めた本庄氏の墓所もあると云う。
元は此処に鮎貝氏と縁の深い大林寺が構えていたらしい。宝暦年間には廃された様だが
...
#
資料に拠れば鮎貝観音は初め、南の飯泉の地に祀られ、飯泉観音と呼ばれていた。その頃から堂守がいたとも伝える。
寛文の頃、大林寺の一隅に修験の泉蔵院が開かれて、のち元禄年中には大町の四郎兵衛によって観音堂が傍に遷されたとか
...
別当の泉蔵院は既に無く、朱印に名を留めるばかりとなった。現在の朱印所は道路をもう少し上がった先の、ちょうちん工房豊邦。
祭礼用の提灯などが見られる。駐車場が案外広くて驚いた
...
■鮎貝郷土史編纂委員会『鮎貝の歴史 前編』1955年
■白鷹町教育委員会『しらたかの歴史をたずねて』1981年
■長井市史編纂委員会『長井市史 第二巻 近世編』1982年
■後藤博『出羽百観音』1996年
■置賜日報社『置賜のお寺めぐり 3市5町の360寺総覧』2001年
■白鷹町教育委員会『しらたかの歴史をたずねて』1981年
■長井市史編纂委員会『長井市史 第二巻 近世編』1982年
■後藤博『出羽百観音』1996年
■置賜日報社『置賜のお寺めぐり 3市5町の360寺総覧』2001年
2019-05-18
previous . . .
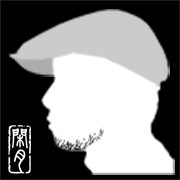
TOM
ぽんとけりゃにゃんとなくよーいよい
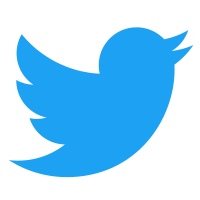 @rondino2106
@rondino2106
